▶ フィリピンの概要
フィリピンは多民族国家

フィリピンは、100以上から一説には200近いとまで言われる民族からなる多民族国家です。タガログ族、セブアノ族、イロカノ族、ヒリガイノン族、ビコール族、ワライ族、パンパンガ族など、主要な民族だけでも挙げればこのように多様性に富んでいます。さらに、数千人しかいない少数民族も存在します。
フィリピン人の大多数はマレー系の民族ですが、インド、中国、アラビア、スペインなどからの移民を祖先とする人々や、彼らとの混血も含め、多様な民族がフィリピン社会を構成しています。
現在では、「フィリピン人」とは、フィリピンに生まれ育った土着の人々を指します。この概念は19世紀半ば以降に広まりました。かつては、スペイン本国生まれのスペイン人と区別して、フィリピン諸島生まれのスペイン人を指すために「フィリピーノ」または「クリオーリョ」という用語が使われていました。同様に、土着の人々は「インディオ」と呼ばれ、スペイン人や中国人の移住者の男性と現地の女性との間に生まれた子どもは「メスティーソ」と呼ばれました。これらの呼称の背景には、インディオやメスティーソの中には、スペインの圧政に耐えかね、改革や自治を求めた様々な運動があったことが考えられます。
フィリピンの民族一覧
タガログ族

タガログ族はフィリピンの主要民族であり、ルソン島を中心にリサール州、ラグナ州、タルラック州、ブラカン州、パターン州などに居住しています。彼らはフィリピンで最も人口が多い民族であり、推定人口は2,000万〜2,500万人に達します。タガログ族はタガログ語を母語とし、この言語はフィリピンの公用語に指定されています。スペインの植民地支配下でカトリック教徒が多数を占め、その影響は現代にも続いています。
歴史的には、スペイン統治、アメリカ統治、そして日本統治といった時代を経て、タガログ族はフィリピンの政治、経済、文化の中心的存在となってきました。彼らは革命運動や独立戦争で重要な役割を果たし、多くの政治家や指導者を輩出してきました。彼らの名前は、河の民や河岸に住む人々を意味する「タガイロッグ(Tagailog)」や、他の地域の民族から来たとする説があります。
タガログ族の文化と影響はフィリピン全体に広がっており、彼らの言語や伝統は国を代表する要素として位置付けられています。その人口はフィリピン全体の約28.1%を占め、地域的にもルソン島以外の地域でも多く見られます。彼らの存在はフィリピン社会の多様性と統合において重要な役割を果たしています。
セブアノ族

セブアノ族は、フィリピンのビサヤ族の主要な民族であり、スペイン人が最初に接触した先住民の一つです。彼らの人口は約1,200万人で、フィリピンでタガログ族に次ぐ規模を持ちます。主な居住地はセブ島を中心に、ネグロス島、レイテ島、マスバテ島、ミンダナオ島の一部にも広がっています。彼らの言語はセブアノ語であり、フィリピン全体で約1,300万人が話しています。セブという名前は、浅瀬を歩いて渡ることを指し、セブ島の地形に由来しています。フィリピン全体の人口の約13.1%を占め、約1,174万人の人々からなり、フィリピン内で2番目に大きな民族です。彼らの文化と言語はフィリピンの多様性に重要な貢献をしています。
イカロノ族

イロカノ族はフィリピンの主要な民族の一つであり、主にルソン島北西部の低地や沿岸地域に居住しています。彼らはイロコス地方の北イロコス州、南イロコス州、ラウニオン州、そしてコルディリェラ行政地域のアブラ州に多く住んでいます。ただし、近年ではルソン島の他の地域や海外にも移住しています。
イロカノ族の人口はおよそ800万人で、フィリピン全体の人口の約11%を占めています。彼らの大部分はキリスト教徒であり、イロカノ語を母語としています。
彼らの主な生業は野菜の栽培、家畜の飼育、およびタバコの生産です。また、イロカノ族はフィリピンだけでなく、アメリカ西海岸やハワイなどの海外にも移住しており、特にハワイではフィリピン系移民の中でも最大の人口を占めています。
イロカノ族はフィリピンの人口の約9.0%にあたる約807万人であり、フィリピン人口において第3位の民族です。彼らの主な居住地は、ルソン島北西部のイロコス地方が中心であり、イロコス・ノルテ州、イロコス・スール州、ラ・ウニオン州、コルディリェラ行政地域のアブラ州などに居住しています。彼らはまた、ルソン島北部、中部、マニラ首都圏、およびミンダナオ島にも移住しています。
ビサヤ族

ビサヤ族はフィリピンの主要な民族の一つであり、ビサヤ地方(ビサヤ諸島)に居住する人々の総称です。彼らはフィリピン人口の40%を占め、ビサヤ諸島の中心に位置するセブ島、パナイ島、レイテ島、サマール島などに居住しています。ビサヤ語を話す人口は約2,000万人に達します。
ビサヤ族はフィリピン内でも重要な存在ですが、社会的にはタガログ語圏と比べるとやや地位が低く、ビサヤ語はタガログ語圏では一般的に話されていません。ビサヤ語圏の人々は、学校教育ではタガログ語や英語が使用されるため、トライリンガルになることが一般的です。
ビサヤ族はセブアノ族、ヒリガイノン族、ワライ族など多くの部族に分かれています。セブアノ族はセブ島を中心に居住し、約1,200万人の人口を持ちます。ヒリガイノン族はパナイ島を中心に居住し、約700万人の人口を有しています。ワライ族はサマール島などに居住し、約310万人の人口を抱えています。これらの部族はそれぞれ独自の言語や文化を持ち、キリスト教徒が大多数ですが、かつてはアニミズム信仰も行われていました。
ビサヤ族はフィリピン全体の人口の約7.6%にあたる約681万人であり、フィリピン内で第4位の民族です。彼らの居住地はビサヤ諸島だけでなく、ボルネオ島のサラワク州やサバ州の一部にも住んでいます。ビサヤ族はビサヤ諸語を話しますが、フィリピン以外の地域では異なる言語を使用することがあります。セブアノ族、ヒリガイノン族、ワライ族などはビサヤ族に属しますが、それぞれ独自の文化や言語を持っています。
パンパンガ族

パンパンガ族は、フィリピンの独立に大きく関わった民族であり、タガログ族と並んでその貢献が特筆されます。彼らはルソン島中部のパンパンガ州を中心にバターン州、ブラカン州、ヌエヴァ・エシハ州、タルラック州などに分布しており、パンパンガ語を母語として使用しています。
パンパンガ族の人口は約300万人で、フィリピンの人口の約3.2%に相当し、フィリピン国内で8番目に大きな民族集団です。彼らの名前の由来は、古代にパンパンガ川の下流に居住していたことに由来します。
主な居住地はルソン島中部の平野部で、特に中部ルソン地方(Central Luzon Region)に多く見られます。パンパンガ州、バターン州、タルラック州、ヌエバ・エシハ州、ブラカン州などが彼らの主な居住地域です。
言語としては、カパンパンガン語(パンパンガ語)が主要な言語であり、タガログ語に近い関連言語としてサンバル語も使用されています。パンパンガ族は、フィリピンの中でも有数の米作地帯に居住しており、大規模な水田耕作が行われています。
ビコラノ族(ビコール族)

ビコール族(ビコラノ族)はフィリピンの主要な民族集団の一つであり、ルソン島東南部のビコール半島および周辺地域に居住しています。北カマリネス州、南カマリネス州、ソルソゴン州、アルバイ州などがその主な居住地域です。彼らはビコール語を話し、その言語はタガログ語に近いとされています。また、彼らの中にはマニラ首都圏にも少数派が住んでいますが、その数は比較的少ないようです。
ビコール族(ビコラノ族)の美人としての評判もあり、その地方出身の女性は美しいとされています。人口はおおよそ600万人で、フィリピン全体の人口の約6.0%に相当します。彼らの主な生業は農業であり、米、コプラ、サトウキビ、トウモロコシ、タバコ、マニラアサなどを生産しています。彼らの文化や言語はフィリピンの多様性の一端を示しており、ビコール地方の文化はフィリピンの文化的景観を豊かにしています。
ワライ族

ワライ族はフィリピンのビサヤ族の中で3番目に大きな民族です。彼らは約310万人の人口を持ち、主にサマール、東レイテ、ビリランなどの地域に居住しています。ワライ族はかつてはラオンという神やアミニズムを信仰していましたが、現在ではほとんどがキリスト教徒となっています。
彼らの母語はワライワライ語であり、フィリピン中部ヴィサヤ地方の東ヴィサヤ地方東部に広く分布しています。主な生業は水田耕作による水稲栽培であり、一部は漁労や商業にも従事しています。
ワライ族の推定人口はフィリピン人口の約3.4%に相当し、約305万人であり、フィリピン国内で7番目に大きな民族です。彼らの居住地はビサヤ地方、レイテ島、サマール島に集中しており、言語はワライ語と一部でセブアノ語が話されています。
ヒリガイノン族

ヒリガイノン族は、フィリピンのビサヤ族の中で2番目に多い民族であり、人口は約700万人ほどです。彼らはパナイ島、西ネグロス、南ミンドロなどの島々に住んでいます。主要な言語はヒリガイノン語であり、イロンゴ語とも呼ばれます。
彼らの名前の由来は、「沿岸部に住む人々」という意味の「ヒリガイノン」から来ており、別名としてイロンゴ族(Ilonggo)とも呼ばれます。推定人口は、フィリピン全体の人口の約7.5%に相当し、約672万人であり、フィリピンの民族の中では5番目に大きな人口を持ちます。
ヒリガイノン族の居住地は、ビサヤ地方を中心に広がっており、マスバテ州、イロイロ州、カピス州、オクシデンタル州などの地域にも居住しています。また、ミマロパ地方のパラワン州や、ミンドロ島、ミンダナオ島にも一部が居住しています。
特に、イロイロ市やバコロド市は、留学先として人気が高まっており、これらの地域にもヒリガイノン族のコミュニティが存在します。
華人

フィリピンには古くから中国系移民である華人が存在し、彼らは経済や貿易、流通の分野で大きな影響力を持っています。福建省を中心に起源を持ち、19世紀中盤以降、政治的な不安定や経済的な機会を求めて移住が増加しました。華人はフィリピン社会に溶け込み、台湾との関係も深い。彼らの経済的成功者は多く、フィリピンの企業や銀行、有名なジョリビーまで含め、様々な分野で事業を展開しています。また、華人社会は多様であり、異なる文化的バックグラウンドを持つ人々が共存しています。彼らの存在は、フィリピンの経済と文化において重要な一翼を担っています。
メスティーソ

メスティーソは、中国人、スペイン人、日本人、アメリカ人などとの混血を総称する言葉であり、元々は白人とラテンアメリカ先住民の混血を指していました。フィリピンでは、スペイン統治時代に重要な軍港であった地域、特にサンボアンガでは、スペイン人との混血者が多く、混血率が高い地域の一つとされています。
過去数百年にわたり、中国系やスペイン人との混血が進み、混血率は高まっています。フィリピンは出稼ぎ国家であり、外国で働く労働者が多いため、他国との混血も多いです。特に日本人やアメリカ人との混血者も多いとされています。
このように、フィリピンのメスティーソは多様な民族の混血者を指し、その地域や歴史的背景によって混血率や混血のパターンが異なります。
パンガシナン族
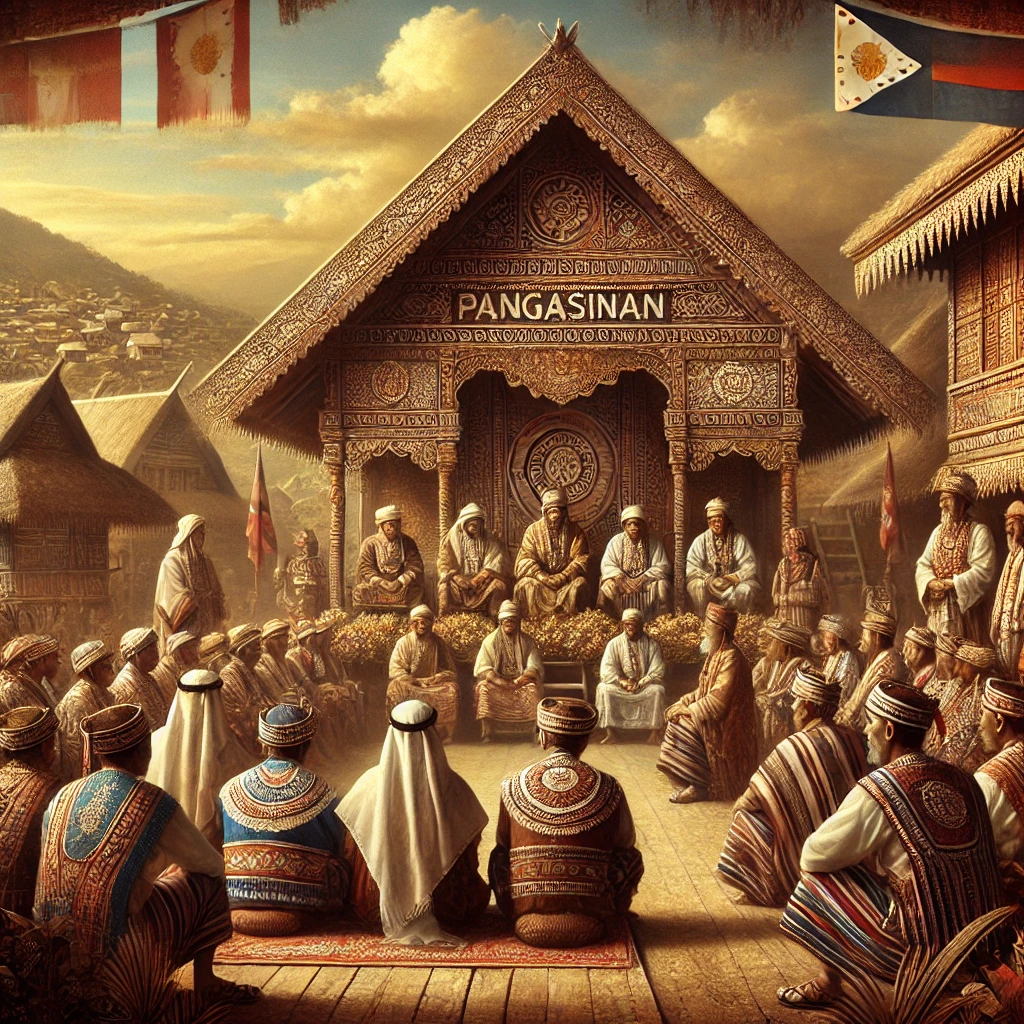
パンガシナン族は、フィリピンの民族の一つで、名前の由来は塩を産する地域を意味する言葉からきている。推定人口は約116万人で、フィリピン人口の1.3%に相当し、ルソン島のイロコス地方や中部ルソン地方に主に居住している。彼らの言語はパンガシナン語であり、イロカノ族との混血が進んでおり、文化的な区別が難しくなっている。そのため、フィリピン人でもパンガシナン族と他の民族を区別することが難しいとされている。
モロ族

モロ族はフィリピンのスールー諸島、パラワン島、ミンダナオ島などに居住するイスラム教徒の総称です。彼らはバジャウ族、ヤカン人、タウズク人、サマル人、マラナオ人などのサブグループに分かれています。
「モロ」という用語は、スペイン人によって初めて使用されました。スペイン人がフィリピンに到達した際、彼らはモロ族を「モロ」と呼びました。当時、モロ族はスペイン人の到来前にフィリピン全域を支配していましたが、スペインとの戦争によりその勢力が衰退しました。
現在、モロ族の人口は約250万人と推定されています。彼らはフィリピンの多様な文化と歴史の一部を形作っており、その存在はフィリピン社会において重要な役割を果たしています。
イゴロット族

イゴロット族は、ルソン島北部のコルディレラ・セントラル山脈の地域に住むマレー系民族の総称です。彼らの名前はタガログ語で「山の人」を意味します。イゴロット族は、棚田稲作を行う高地イゴロット族と、陸稲栽培を移動耕作する低地イゴロット族の二つの主要なグループに大きく分かれています。
特に高地に住むイゴロット族は、美しい棚田を作ることで知られています。彼らの農業システムは、段々状の棚田を利用して斜面の地形を活用し、水源を確保しています。これは、イゴロット文化の重要な要素であり、彼らの生活と経済において中心的な役割を果たしています。
イゴロット族の宗教は精霊信仰に基づいています。彼らは自然界の精霊や神々を崇拝し、彼らの信仰は彼らの日常生活に深く根付いています。山々や川、森林など自然の要素に対する畏敬の念が、彼らの宗教的信念に反映されています。
イフガオ族

イフガオ族はフィリピンの少数民族の一つであり、イゴロット族に属します。彼らはフィリピンの北部に位置するイフガオ州に住んでいます。イフガオ族はイフア語を話し、独自の文化と伝統を持っています。
彼らの最も特筆すべき特徴の一つは、山岳地帯において石垣を組んで作られた棚田です。これらの棚田は、標高1,000〜1,500メートルの山腹に広がっており、水稲耕作に利用されています。彼らの農業技術と棚田の管理は、長い歴史の中で発展しました。
イフガオ族の社会では、棚田や水牛の所有数などが社会的な階層を決定する要素とされています。このような社会的階層は、土地と資源の管理に関連しています。
彼らの最も有名な棚田は「バナウェ棚田」であり、約2000年前に造られたと言われています。これらの棚田は、コルディレラ山脈にあり、その景観の美しさと技術的な偉業から1995年に世界遺産に登録されました。
近年、バナウェ棚田周辺は観光地として開発され、ホテルや施設が整備されています。観光客にとっては、イフガオ族の文化や棚田の景観を体験する機会となっていますが、同時に環境保護や文化の持続可能性についての課題も浮上しています。
ボントック族

ボントック族は、フィリピンのルソン島北部に居住するイゴロット族の一部であり、その人口は約5,000人ほどと推定されています。彼らの文化は、かつて首狩りや頭蓋崇拝、生贄などの要素を含んでいましたが、現在はほとんど消滅したとされています。
彼らの文化は、他の一部の民族と類似しています。例えば、インドのナガ族や東インドネシアのニアス島民と同様に、ボントック族も稲作や畜産などの農耕生活を営みながら、原始的な生活を送っていました。
ボントック族は、ボントック語を母国語として話すだけでなく、イロカノ語も話します。彼らの言語や文化は、フィリピンの多様性と深い関連があり、彼らの歴史や伝統はフィリピンの民族的な多様性の一部を形成しています。
イバロイ族

イバロイ族は、フィリピンのベンゲット州南部に住むイゴロット族の一部です。イゴロット族はフィリピンの北部山岳地帯に居住し、その文化や生活様式は山岳地帯の厳しい環境に適応して発展してきました。
イバロイ族は、ベンゲット州のバギオ市を含む一帯に主に住んでいます。バギオ市はフィリピンの高原都市として知られ、観光地としても有名です。イバロイ族の一部は農業や手工業に従事しており、山岳地帯の環境に適した農作物を栽培しています。
イバロイ族の文化には、伝統的な服装や建築、祭り、音楽などが含まれています。彼らの生活は、自然環境との調和や共同体の重視に基づいており、伝統的な生活様式を大切にしています。近年では、近代化や観光業の影響により、イバロイ族の生活や文化に変化が見られることもありますが、彼らの伝統や価値観は多くの場所で引き続き尊重されています。
イスナゴ族

イスナゴ族は、フィリピンのルソン島に位置するアパヤオ州に居住するイゴロット族(Cordillerans)の一部です。イスナゴ族は、イスナゴ語とイロカノ語を話す民族で、彼らの文化や言語はフィリピンの先住民族の豊かな多様性の一部を形成しています。
イスナゴ族の伝統的な生活は、農耕と山岳地帯での生活に根ざしています。彼らの主な作物は米であり、山岳地帯の厳しい環境にもかかわらず、農業と家畜の飼育を通じて生計を立てています。
イスナゴ族の文化には、祭りや儀式が含まれており、これらは彼らの社会的な結束を強化し、伝統を維持する重要な役割を果たしています。また、彼らの伝統的な衣装や工芸品も注目に値します。
近年、イスナゴ族の生活は現代化の影響を受けつつありますが、彼らの伝統や文化はコミュニティの一部として重要性を保ち続けています。
カリンガ族

カリンガ族はフィリピンの北部にあるカリンガ州に住む民族の一部で、主にイゴロット族に属します。彼らはカリンガ語とイロカノ語を話すことが一般的です。
カリンガ族は、その伝統的な刺青文化で知られています。これを「カリンガ・タトゥー」と呼びます。このタトゥーは、彼らの文化や社会的地位、あるいは勇気や英雄的な行為などを象徴するために用いられます。カリンガ族の男性はしばしば胸や腕にタトゥーを入れ、これは彼らのアイデンティティの一部として重要視されています。
また、カリンガ族は農耕や狩猟、織物などの伝統的な生活様式を維持しています。彼らの文化は豊かで、その伝統的な音楽や舞踏、祭りなども重要な要素です。
カンカナイ族

カンカナイ族は、フィリピンのベンゲット州北部に居住するイゴロット族の一部です。彼らは独自の文化や伝統を持っており、その中には特に興味深い習慣が含まれています。
カンカナイ族の中で、男性と女性はそれぞれ別々の「寮」に住んでいます。これは、性別に基づく社会的な構造の一部であり、男性寮と女性寮はそれぞれ異なる役割と機能を持っています。
特筆すべきは、女性寮で行われる「言い寄り」という独自の習慣です。この習慣では、男性が女性寮に訪れ、興味を持っている女性に対して愛の告白や求婚を行います。これは、カンカナイ族の恋愛や結婚における重要な要素の一つであり、彼らの文化や社会的結びつきを形成する上で重要な役割を果たしています。
カンカナイ族の独自の言語であるカンカナイ語も、彼らの文化と密接に結びついています。この言語は、彼らの伝統や生活様式を反映しており、彼らの共同体のアイデンティティや誇りの一部となっています。
カンカナイ族は、フィリピンの多様な民族グループの中で、独自の文化と伝統を維持し続けています。その社会的構造や独自の習慣は、彼らが長い歴史の中で築いてきた豊かな遺産の一部であり、フィリピンの多文化的な景観を豊かにしています。
少数民族

フィリピンの少数民族には、山岳地帯に住むネグリト、ボントック、イフガオなどが含まれます。彼らはフィリピン各地の山岳地帯や南部のミンダナオ島、スールー諸島、パラワン島に居住し、中北部の低地住民とは異なる文化や生活様式を持っています。少数民族の人口は、全体の約10%程度と推定されています。
フィリピンの少数民族は、主にムスリム(モロ族)と山岳地域の住民の2つのグループに分類されます。アメリカの支配時代には、「非キリスト教徒部族民」という名前で少数民族が呼ばれ、彼らは後進的で野蛮な存在と見なされていました。特にモロの反乱などの事件がありました。
少数民族の中には、国会議員や地方議員も出ていますが、彼らはしばしば地域の支配者である「ボス」として知られ、少数民族の利益や権利が政治的に反映されないことがあります。また、彼らは宗教的な違いや無知からくる偏見に晒され、差別の対象となることもあります。
その他
フィリピンには、多様な民族集団が存在し、彼らの歴史や文化は国の多様性を形作っています。以下に、フィリピンの主な民族集団についてまとめます。
- モロ族:ミンダナオ島などの南部に居住するイスラム教徒の集団です。モロ族にはバジャウ族、ヤカン人、タウスグ人、サマル人などが含まれます。
- ネグリト族:フィリピンに最初に移住してきたとされる最古の民族です。マレーシアを経てフィリピンに移住してきたと考えられています。彼らの特徴は、短い身長や暗い肌などが挙げられます。ネグリト族の一部はルソン島、パラワン島、ネグロス島、ミンダナオ島の山岳地帯や海岸地帯に暮らしています。
- その他の山岳族:アグタ族、アイタ族、アエタ族、バタック族、アティ族、ママヌワ族など、山岳地帯に居住している様々な民族が存在します。これらの民族は、古代からの伝統を守り、独自の文化や生活様式を維持しています。
これらの民族集団は、フィリピンの社会や文化に多様性をもたらし、国の豊かな遺産の一部となっています。
まとめ
フィリピンは、多様な言語や文化が共存する国であり、少数民族も含めると約172の言語が話されています。これらの言語の多くはアウストロネシア語族に属していますが、それぞれが独自の文化や言語構造を持っています。この多様性は、フィリピンを訪れる際に異文化体験を提供し、視野を広げる機会となります。
フィリピンでは、各地でフィエスタと呼ばれるお祭りが盛んに行われており、先住民族の伝統文化を紹介するパレードや民族衣装を着た現地の人たちによるパレード、伝統舞踊などが行われます。これらのフィエスタに参加することで、フィリピンの土地の文化や伝統を深く理解し、濃厚な異文化体験をすることができ
▶ フィリピンの概要

 0120-905-768
0120-905-768 0120-905-768
0120-905-768


